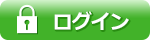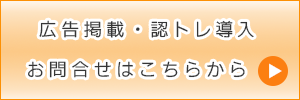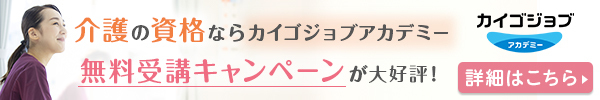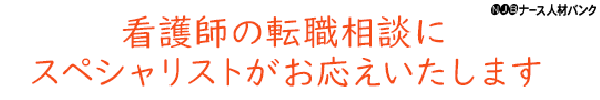【山村基毅さん連載コラム(第2回)】保育園問題との対比から考える認知症介護離職

保育園問題より見えにくい特養待機問題
「保育園落ちた日本死ね」が話題となり、国会でも取り上げられたのは記憶に新しい。 それだけ待機児童の問題は、広く、そして深く浸透しているということなのだろう。 しかし、介護において「特養(特別養護老人ホーム)落ちた日本死ね」というフレーズは出てこない。
老人福祉施設に入所を希望していながら待機する「老人」が数十万人といわれているのに、である。いや、インターネット上には介護にまつわる悲痛な叫びがないわけではないのだが、そうした声はなかなか広まってはいかない。

理由の一つは、子育てのもつ希望や未来というイメージに対して、介護は徒労感、やがて訪れる「死」が対置されるからだろう。
それと、もう一つ、これは一連の報道を見ていて気づいたのだが、子育てに携わるのは20代、30代の母親、父親である。介護のほうは、老老介護という言葉が取り沙汰されるように、60代から70代、下手をすると80代の息子や娘、あるいは夫や妻である。すでにリタイアした者が上の世代の面倒をみている、というように捉えられがちなのだ。そのこと自体、まんざら誤ってはいないものの、しかし、リタイアしていない者も少なくはない。このとき、介護する者たちは「一億総活躍」の枠からこぼれ落ちてしまっている。
介護と医療の垣根を超えた居場所つくりが介護離職問題を打開する
さて、奈良県にある精神科病院「ハートランドしぎさん」の取り組みをレポートした『認知症とともに生きる』には、何人かの患者の家族が登場する。
認知症の場合、その周辺症状や身体合併症のため老人福祉施設からも入所を拒まれる例が多々あるのだ。うまく老人福祉施設と巡り会えず、やっとたどり着いたのが、この病院であったという例も少なくない。
たとえば、共働きの50代夫婦は、認知症の母が入所できる施設を見つけられなかったため、いっときは仕事も手につかない状態に陥ってしまったという。「ハートランドしぎさん」が母を受け入れてくれたため二人とも仕事を辞めることなく、病院にやってきては母と触れ合えるようになった。私が話を聞いた時点で入院期間は2年を超えていた。普通の病院なら3ヶ月ほどで退院させられるのだが、ここでは長期にわたっての世話が可能なのだ。それこそ「特養落ちた」者たちには福音となっているのである。
介護者の生の声が介護離職問題解決に向かう原動力となる
4月に毎日新聞が発表した在宅介護者へのアンケート(245人が回答)によれば、介護によって精神的・肉体的な限界を感じたことがあるという人が73%、心中を考えた人が20%もいたという。彼らの負担を肩代わりすることは労苦を減らすだけでなく、そこで費やされるエネルギーを他に向けられることでもある。それは子どもを保育園に入れられないため仕事に就けずにいる親と同じなのだ。
疲れ切ってしまう前に、介護する者たちは、もっと声をあげてもいいだろう。
(画像はイメージです)
【主な著書】
▼関連記事
【山村基毅さん連載コラム(第1回)】鉄道事故の判決から考える認知症ケア
認知症のケアと介護
- 認知症は予防できます!! –認知症「予防」のための3資格-
- 認知症予防医/広川慶裕医師の新刊「脳のスペックを最大化する食事」7/20発売
- 認知症予防医/広川慶裕医師の新刊「潜伏期間は20年。今なら間に合う 認知症は自分で防げる!」
- 広川慶裕医師の、認知症予防のことがよく分かる『認トレ®️ベーシック講座』開講!
- 知ると知らないじゃ大違い!民間介護保険って何?
- 酸化ストレスを減らすと認知症予防に!秘密はサプリメント
- ユッキー先生の認知症コラム第92回:あるべき姿の認知症ケア
- 認知症専門医による認知症疾患啓発イベントを開催
- ポイントは食生活にあった。認知機能維持に必要なのは・・・
- 認知症予防は40代から!摂ると差が出る栄養素とは。
- 山口先生のコラム「やさしい家族信託」第17回:Q&A 外出自粛で、認知機能の低下が心配。家族信託、遺言、後見、今できることが知りたい
- 【広川先生監修】5分で分かる認知機能チェック(無料)はこちら
- 認知症は予防できるの?
- 認知症の種類とその詳細はこちら