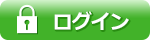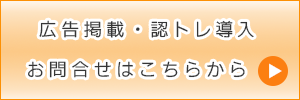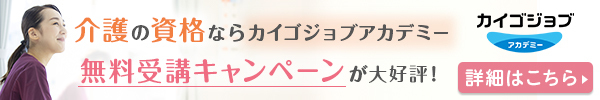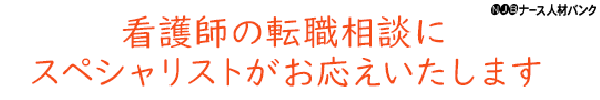偏見を溶かしたい―。VR認知症体験プロジェクトに込められた想いとは
「認知症に対する偏見は想像以上に広がっていて、“認知症になりたくない”や“認知症を予防したい”などといった社会的な通念が、認知症のある人を生きづらくしている」そう話すのは、VR認知症プロジェクトを手掛ける株式会社シルバーウッド(東京都港区)の代表、下河原忠道さん。
認知症の正しい理解を社会全体に広げるにはVRを利用した“認知症の一人称体験”が有効だと訴え、全国各地で体験会を開いている下河原さんに、プロジェクトに込めた想いを伺いました。(聞き手:吉岡名保恵)
体験会で明らかになる認知症への偏見
ゴーグル型のVR端末とヘッドホンを装着すると、目の前に360度、広がる別世界。第一作目として作られた『ここはどこですか』は、電車に乗っていて、乗換駅が分からなくなった主人公の目線でストーリーが始まります。不安な気持ちを抱えたまま、電車を下車した主人公は駅員に「ここはどこですか?」と尋ねるのですが…

この作品を見終わった体験者に、下河原さんはよく「このストーリーの主人公は、認知症のある人と思いますか?」と問いかけるようにしています。すると、ほとんどの人は「認知症ではないと思う」と答えるそうです。なぜかと聞けば、「行き先はちゃんと分かっているから」、「人にちゃんと声をかけられているから」「そもそも電車に一人で乗っているから」など。
一方で、若年性認知症の当事者である丹野智文さんは、この映像を見て、自分も同じような経験がある、と言い切ったそうです。「認知症なら行き先も分からないはず、人にちゃんと質問することもできないはず、といった思い込みがあるんです。いかに認知症イコール重度の記憶障害、と思い込んでいる人の多いことか。本当に“偏見のオンパレード”なんです」(下河原さん)。
もともとは、登場人物が認知症かどうか、に焦点を当てて作った映像作品ではありません。下河原さんは認知症のある・なしに関わらず、困っている人がいたら相手の立場に立ち、思いやりを持って接する必要性を問いたかっただけ。しかし、副産物的に明らかになったのは、認知症の当事者と、そうでない人の感覚のギャップでした。
だからこそ下河原さんは、VR認知症体験を通して「周囲にも認知症があって困っている人がいるかもしれない。そのときどうしたら良いのか」考えるきっかけをつかんでもらおうとしています。例えば、映像に出てきた駅員は、なぜあのように答えたのか、対応の仕方はどうだったのか―。最初は「認知症ではないと思う」と答えた人たちも、下河原さんからそう問いかけられると、ハッと立ち止まって考えるようになると言います。
認知症の中核症状を描く

高齢者住宅の運営を手掛けている下河原さんは以前から、入居者の様子を見ていて、認知症に対する偏見を助長させている社会に大きな問題があると感じてきました。
「誰だって、認知症になりたくてなるわけではない。認知症があっても、普通に生きられる社会を作るにはどうしたら良いのだろう」。そう考えていたときに出合ったのがVRの技術。VRを利用すれば、認知症の一人称体験ができ、認知症のある人の行動や気持ちを知るきっかけになると考えたのです。「認知症に対する偏見をいい具合に溶かしていきたい。それがこのVR認知症プロジェクトの“肝(きも)”なんです」。
認知症を取り上げた既存の映像作品は、「行動・心理症状(BPSD)」と呼ばれる周辺症状をクローズアップするものがほとんど。しかし、下河原さんは「行動・心理症状(BPSD)」ではなく、「中核症状」について描いた作品を作ろうと考えます。
「ふと気づいたんです。認知症について語るとき、必ず第三者は行動・心理症状(BPSD)の話ばかりをする。でも本来、認知症のある人が何に困っているのか、何が原因でそのような行動をするのか、分かろうと思えば、中核症状について理解していないと難しい。どんな中核症状があるのか知らずして、とにかく認知症=記憶障害とひとくくりにしている社会が問題なんだと思いました」。
そこで2016年3月にVR事業部を立ち上げ、映像作品の企画から脚本、撮影、編集まですべて自社で開発をスタート。全く新しい分野への進出だっただけに最初は本当に手探りでしたが、一つ作品を作っては体験会を開き、反応を見ながら次の作品につなげていく日々だった、と言います。
4作目として取り上げたのは幻視が見える「レビー小体型認知症」。この作品では、当事者であり、『私の脳で起こったこと レビー 小体型認知症からの復活』の著者である樋口直美さんに脚本や演技指導、映像編集などの協力を得ました。
「樋口さんにはVR体験会にお越しいただき、お話をしてもらうこともあります。ご本人の体験を映像にしたうえで、どのようなことを社会に伝えたいのか、ご自身で語っていただけば、よりリアリティーが増すのではないか、と思ってお願いしました」。そこには、認知症のある人や支える家族が、認知症についてきちんと周囲に話せる社会になってほしい、という下河原さんの願いが込められています。今後は、若年性認知症の当事者である丹野智文さんの体験映像も制作する予定だそうです。
認知症に対する想像力を強く持って
2016年にVR体験をしたのは、およそ1,500人。下河原さんは「認知症という社会課題に立ち向かおうとしたら、専門家や家族だけではどうしようもないんです。困っている人を見かけたとき、もしかしたら、この人は認知症のある人かもしれないと誰もが想像力を持って接することができれば、認知症のある人にとって生きやすい社会に変わると思います。だからこそ、一般の人たちに広くVR体験をしてもらいたい、という想いが強い」と語ります。
VR体験会の開催は、中学校や高校など教育機関からの依頼も増えてきています。下河原さんは「若者たちは、きっと新しい担い手として社会を変えてくれるはず。中高生は自然な発想で認知症に向き合ってくれるから期待しています」として、学校では無料で体験会を開いているそうです。

これから力を入れていきたいのは、ファシリテーターの養成。「単純に映像だけを見て、認知症を理解するのは不可能。そこで必要になってくるのが、正しい知識を身に付け、体験会を有意義に進行できるファシリテーターです。ファシリテーターが育てば、体験会をシステム化してもっとたくさん開催できるはず」。
さらに下河原さんは、そのファシリテーターを中高生に任せてみたい、という構想も持っています。「中高生が自分の言葉で認知症と向き合っている姿を、一般市民が見たときにどう感じるか。中高生が自分たちで体験会を企画するところから始めてもらいたい」
企業からの開催要望が増加
5作目として完成したのは、岩手医科大学神経内科・老年化准教授だった故・高橋智先生が作った『やすお じいちゃん物語』をモチーフとした作品です。これは認知症のある人を支える家族向けのストーリー。下河原さんは「認知症の行動・心理症状(BPSD)が悪化する一番の問題が、家族など周囲の人との関係障害にあると思っています」と話し、周囲の人たちの言動が、どれほど認知症のある人を追い込んでいくかを体験できる内容だと言います。
実際、介護離職の問題が深刻化する中、社員を対象にVR体験会を開きたい、という要望も増えてきているそうです。「家族の認知症について早い段階で診断や相談ができ、どのようにサポートすれば良いのか指南してもらえれば、お互いの関係性を悪化させず、認知症の症状を押さえられることもあります。自分の親に介護の必要が出てきたとき、どのようなリソースが地域にあって、どういうふうに家族が接したら良いのか…。企業側も社員の認知症に対するリテラシーを上げる活動をしなければいけない、と気づき始めているのではないでしょうか」。
先日は厚生労働省老健局でも職員を対象にVR体験会が開かれました。VR認知症体験を通し、今までにない視点で、認知症を捉える機会を広げられないか、国としても検討は始まっているのです。
今後は、例えば金融機関で働く人たちを対象に、認知症のある人が窓口に来た場合の対応について考える映像を作るなど、専門的なコンテンツも手掛けられないか構想が進んでいる、という下河原さん。
「世の中の社会的課題を自分の頭で想像し、アクションプランにまで落とし込めるかどうか、というところでは、VR体験はとても有効です。ビジネスとして継続性も担保しなければいけないので、色々な企業さんに協力をしてもらって四苦八苦していますが、活動は粛々とやるしかありません。今後は認知症体験を足がかりに、さまざまなマイノリティーの一人称体験ができる機会を提供していきたいと考えています」。挑戦は、まだまだ始まったばかりなのです。
VR認知症体験については、株式会社シルバーウッド (電話:03-3401-4001、Eメール:VR@silverwood.co.jp)まで。
- 認知症は予防できます!! –認知症「予防」のための3資格-
- 認知症予防医/広川慶裕医師の新刊「脳のスペックを最大化する食事」7/20発売
- 認知症予防医/広川慶裕医師の新刊「潜伏期間は20年。今なら間に合う 認知症は自分で防げる!」
- 広川慶裕医師の、認知症予防のことがよく分かる『認トレ®️ベーシック講座』開講!
- 知ると知らないじゃ大違い!民間介護保険って何?
- 酸化ストレスを減らすと認知症予防に!秘密はサプリメント
- ユッキー先生の認知症コラム第92回:あるべき姿の認知症ケア
- 認知症専門医による認知症疾患啓発イベントを開催
- ポイントは食生活にあった。認知機能維持に必要なのは・・・
- 認知症予防は40代から!摂ると差が出る栄養素とは。
- 山口先生のコラム「やさしい家族信託」第17回:Q&A 外出自粛で、認知機能の低下が心配。家族信託、遺言、後見、今できることが知りたい
- 認知機能チェック